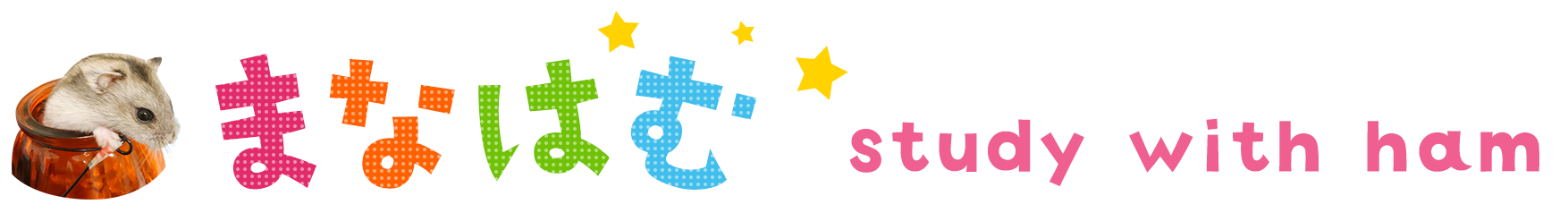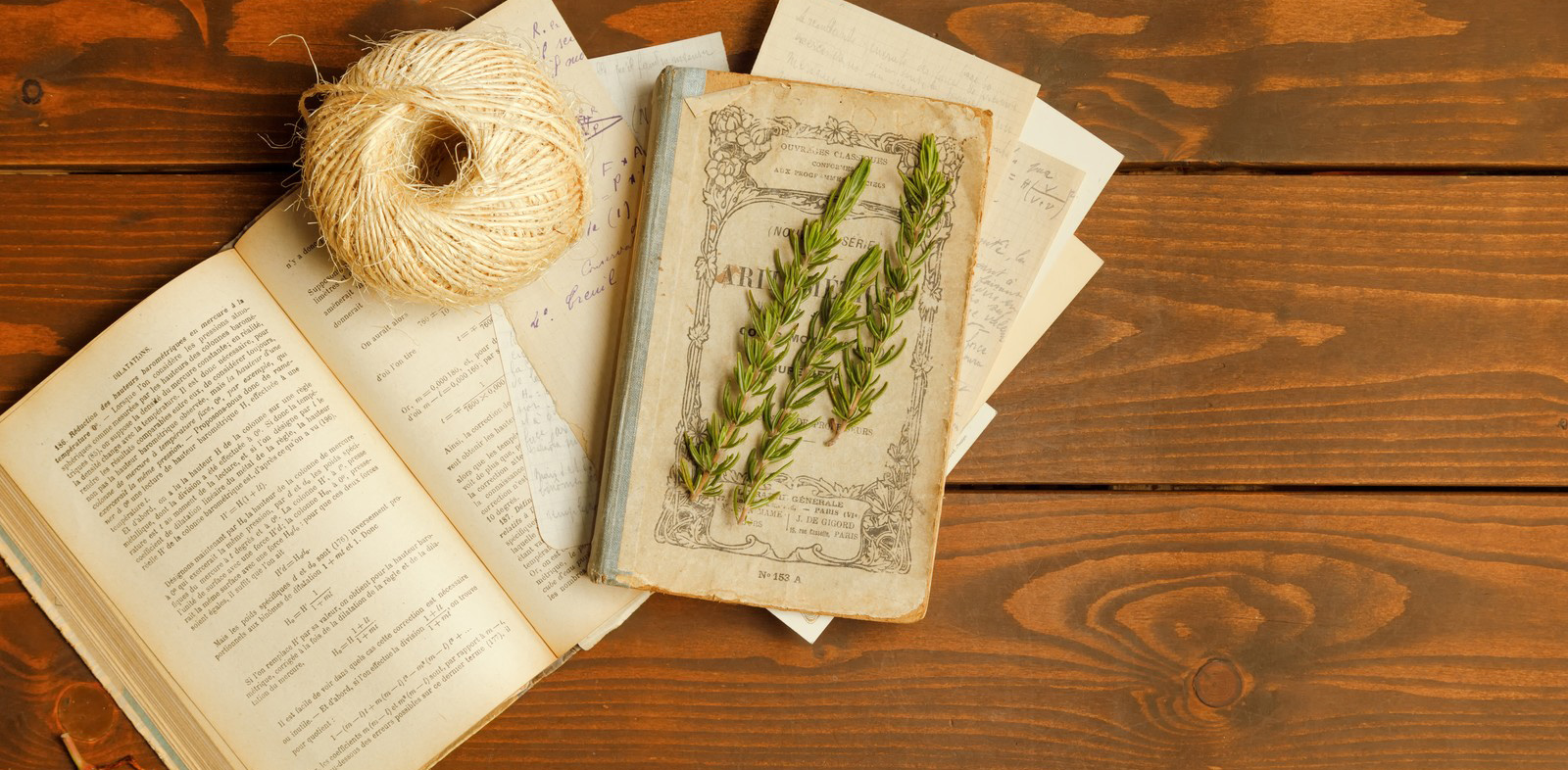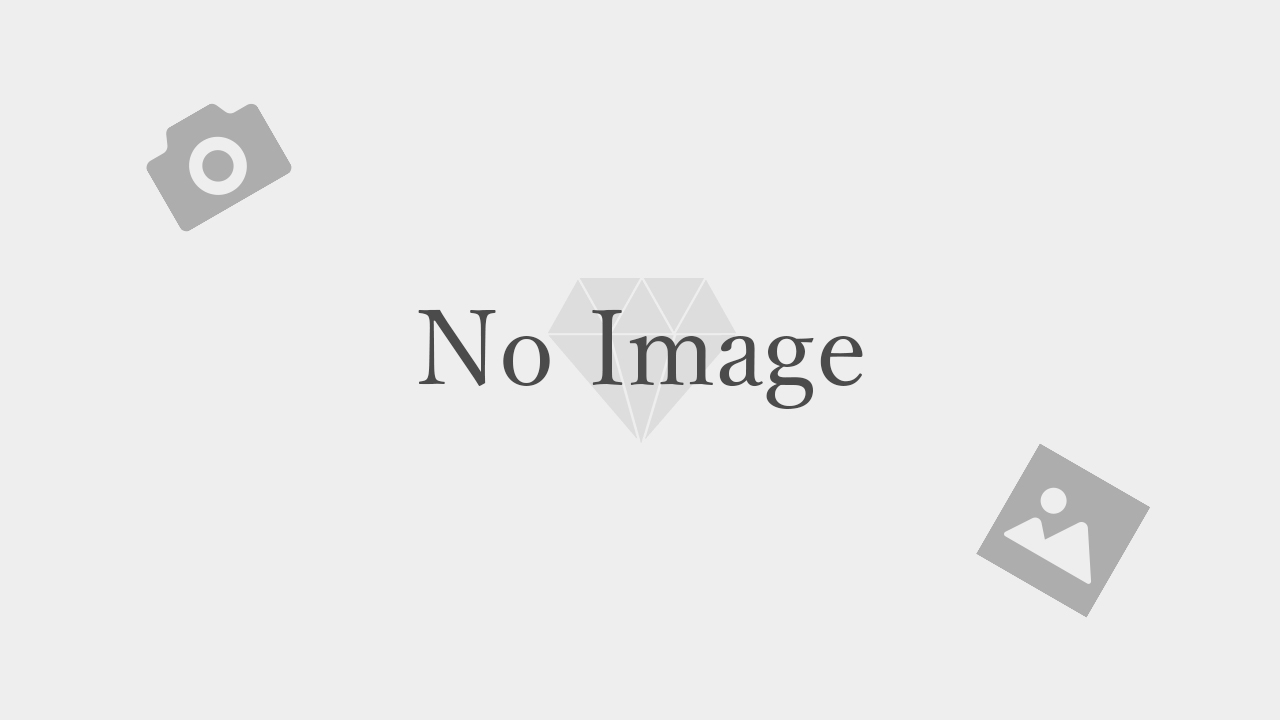今日より学校が休校に入りました。しかし当然のごとくドッサリと宿題が出されています(汗)早めに終わらせて、予習と復習をしっかりとしておきたいなと考えています。
学年末テストが帰ってきました。
点数が悪いものもあったので、あまり思わしくない成績だろうなあ〜と思っていたのですが、今回もそこまで下がってもいませんでした。
感触としては、2学期の期末テストと同じくらい。
数学は点数は悪かったのですが、席次は上グループに入るくらいのもので、これはびっくりしました。
平均点がかなり低かったようなので、全体的に難しい問題だったのでしょうね。
さて、息子のテストの特徴がだんだんとわかってきたのですが、5教科に比べて副教科の点数が悪い・・・^^;;;
3回期末テストやって、毎回その感想なので、これは間違いなさそうです。
どうやったら、副教科の点数が上がるのかな〜〜。。
副教科はほぼほぼ暗記科目ではありますが、うちの中学校は1週間前のテスト発表です。
おそらく、時間が足りずに勉強が不十分になることが最大の原因ではないか、と思われます。
これは、今後の課題ですね〜〜^^;;
「わからない」を「わかる」に変えるのが勉強だけど
最近、少し発想の転換をしています。
勉強においては、「わからない」問題に印をつけるなどして、そこを繰り返しやる。
こういう勉強法は王道だと思うのですが、息子にはどうにもそのやり方はあんまり好感触ではないのです。
なぜなら、「間違えることが嫌」だから。笑
なので、ちょっと発想を転換して「わからないを、わかるに変える」のではなくて、「できること」を増やしていく、という発想に変えて行くことにしました。
どういうことかというと、「しっかり定着した問題を増やして行く」という感じです。
できる問題はとにかく、即答できて当たり前!になるくらいまでに定着させていって、そこで初めて、「できる問題をもうひとつ増やす」という感じです。
わからないところを繰り返して潰して行くという感じとはちょっと違います。
息子はこの方法だと自信がなくなってモチベーションダウンになってしまうようで^^;;;
定着している問題のグループに、わからない問題を少しずつ入れて行く、という感じといったらいいでしょうか。
要は、できないものにフォーカスを当てるのではなくて、できることにフォーカスを当てて、それを増やして行く感じです。
もちろん、できない問題ばかりを必死でやり抜くことができるのであれば、その方がいいのですが、息子の場合はこのやり方の方が合ってるようで、しばらくはこれでいこうかなと思っています^^
できることに目をむけていく。
これって発達障害の子を育てる基本みたいに言われていることとも似ているような^^ 不思議な感じですね。
長い休校期間になりますが、中1の勉強もまだ残っていますし、中2の勉強の予習もしたいし。
やりたいことは盛りだくさんですね^^
そんな息子ですが、今日は一年生のクラスの子達とお別れになることを、それはそれは惜しんでいました。
先生も生徒も、本当に良いクラスでしたからね〜
校区が変わって最初は心配でしたが、小学校のいじめっ子ともオサラバできましたし、新しい学校は本当に落ちついていますし。
校区を変わって心の底から良かったと思っています。
クラス替えした2年生のクラスでもいいことがたくさん待っているはず!^^
思い出を大切に、頑張っていこう!!
にほんブログ村